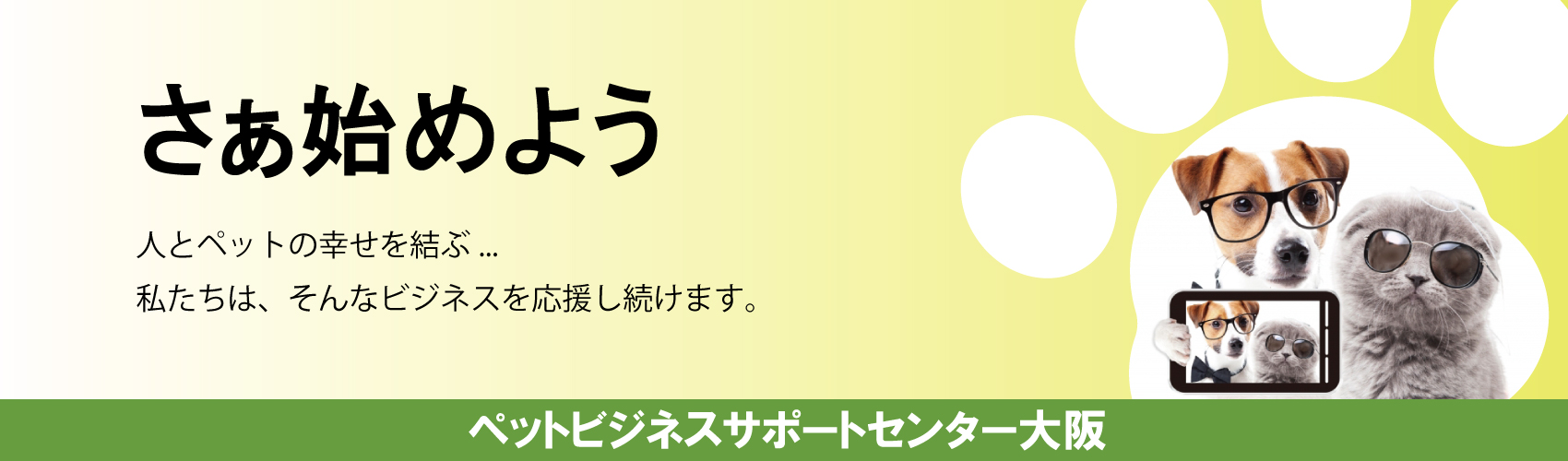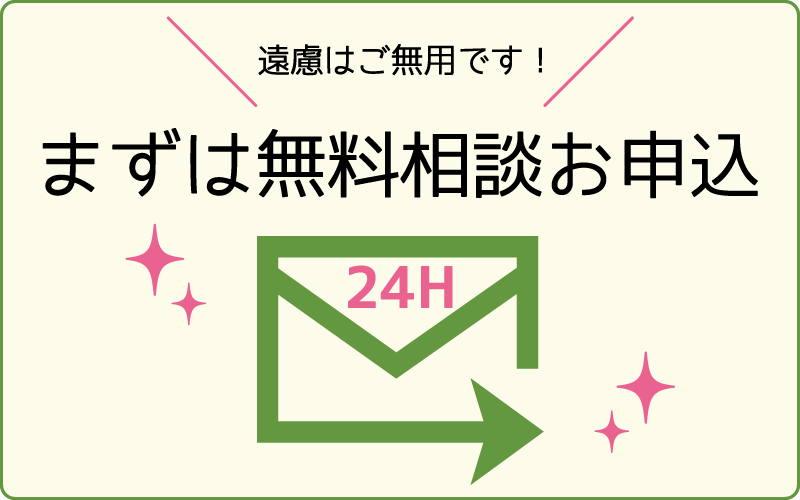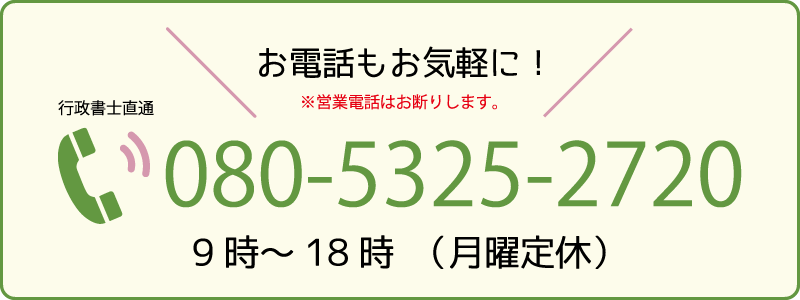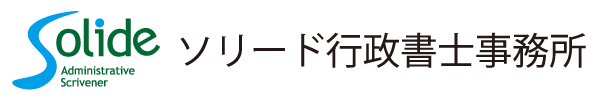ペットビジネス起業・開業・独立サポート

ペットビジネスの起業・開業・独立に不可欠な、行政機関への許可・登録・届出等の申請手続きを代行します。
ペット業界専門、かつ行政機関への各種手続きの専門家である行政書士が、複雑な申請をスピーディーに確実に行いますので、事業主様は本業のご準備に専心いただくことができます。
登録を拒否されたり、許可が受けられない場合は、報酬を全てお返しする「安心の全額返金保証付」です。
ビジネスのグランドデザイン構築段階からのご相談も大歓迎いたします。
ペットブリーダー開業
その殆どが個人事業主で構成されるペットブリーダーの市場は、個人での新規参入が容易なビジネスと言えます。
コロナ禍のペットブームによるペット販売価格の高騰が、2024年頃から落ち着き始め、繁殖用の生体を購入する費用も以前と比べると随分抑えることができるようになりました。
市場のペット販売価格は周期的なブームに影響を受けます。
しばらくの間は安価な傾向が続くことにより、ブームに乗って開業をしたり、ブームで無謀な拡大や放漫経営をしたブリーダーの淘汰が進みます。
ブリーダーの減少に伴いペットの繁殖総数が減少することにより、少しずつ価格が上昇し、次のブームの周期を迎えることになります。
2025年~2028年頃については恐らくブームの谷底になると思われ、新規開業の絶好のチャンスになりそうです。
投下する資本が少なくて済み、自宅でも容易に起業・開業できまることから、専業と言うよりは、副業・兼業での可能性を大いに感じるビジネスでしょう。
犬のブリーダー
猫のブリーダー
ペットサロン(美容室)・ペットホテル開業
大手のペットショップや動物病院が併設するペットサロンと個人事業主が経営する小規模サロンが混在する市場です。
ペットブームによる飼養頭数の増加と、コンパニオンアニマル化や長寿化により、安定的な市場規模を形成しています。
ペットホテルについては大規模化や病院併設が目立ち、人間のホテル並のサービスを提供する事業者も増加しており、スペースの確保が難しい小規模店は、この分野で大きな収益を目指すことは難しいでしょう。
反面ペット美容については、技術力と接客が事業成功における大きなウエイトを占めることから、小規模であっても努力次第では充分に成功できる余地が残るビジネスと言えるでしょう。
ペットの老齢化を見越し、老齢ペットに負担の少ない美容の施術や、訪問によるサービスを導入するなど、人間の介護サービスに類似するようなサービスにも期待が集まっています。
ペットサロン(美容室)・ペットホテル
ペット向け民泊サービス開業
ペットの飼養経験のある主婦や動物病院やペットショップでの勤務経験がありリタイヤされた方、そしてペットは大好きだが年齢的な理由で飼う事を断念した老齢の方が自宅で行うことができるビジネス。
ペット関連の副業ビジネスとして今後注目をあびる存在になる可能性もあります。
ペットを溺愛する傾向が強くなり、従来のペットホテルへ預けることへの拒否感を持つ飼い主も少なくなく、普段と変わりない環境にペットを預けることのできるペットの民泊サービスは、可能性を秘めたビジネスと言えるでしょう。
反面、収益については大きなものを期待することは難しく、副収入として価値が見いだせるか、そしてやりがいや生きがいに結びつくものであるかをしっかりと検討したうえで開業されることをお薦めします。
自宅での開業が基本となり開業コストが掛からないのが魅力ですが、サービス自体の知名度が低く、集客方法が課題となるでしょう。
犬のホストファミリー・ペット向け民泊サービス
ペットカフェ(ふれあい目的)開業
ペットカフェ市場は、「体験型サービス」「癒し産業」としてニーズは堅調であり、観光業とも相性が良い市場です
SNSの普及による情報共有が後押し、国内需要のみならずインバウンド需要も拡大しています。
国内需要としては、ペットを飼いたいが、住環境や経済的事情で飼えない層が増えており、気軽に動物と触れ合える場として人気があります。
インバウンド需要としては、特に猫カフェ、フクロウカフェ、ブタカフェ、ハリネズミカフェなどが海外観光客に好評で、日本独自の観光体験として注目されています。
市場が成熟化すると共に競争が激化しており、容易い市場とは言い難いですが、小規模であっても、珍しい動物とのふれあいや、コンセプト(和風空間やワーケーション等々)を重視するなどの差別化を図れば、成功の可能性は充分に残されています。
また、動物福祉への配慮や衛生管理、飼育・展示方法など法規制を遵守した運営が求められます。
ペットカフェ(ふれあい)犬・猫・鳥・ブタ・小動物(エキゾチックアニマル)カフェ
ドッグトレーナー(訓練士)・しつけ教室・幼稚園開業
ペットのコンパニオンアニマル化により、擬人化や溺愛が原因で、しつけの出来ない飼い主が増加しており、ドッグトレーナー(訓練士)やしつけ教室等は、今後さらにニーズが高まって行くものと思われます。
犬の訓練所・しつけ教室・幼稚園を開業するには一定のスペースの確保が必要であり、それなりの資本が必要なります。大手の参入もあり、容易い市場とは言い難い部分がありますが、小規模であっても顧客の利便性を追求したデイサービスの提供により固定客化を図れば、成功の可能性は充分に残されています。
出張(訪問型)のドッグトレーナーについては大資本の参入が無く、初期投資額も非常に少ないことから、小規模事業者でも成功の可能性が充分に残された市場と言えます。
成功の鍵は、ホームページやSNSを利用して如何に集客できるか?
送迎の効率を考えると、地域密着型のビジネスに徹することが重要であり、地域名を織り込んだSEO対策やMEO対策、そしてSNSとの連携が重要となります。
ペットショップや動物病院と提携し、出張トレーナーとして、しつけ教室や幼稚園の運営に関わることができると、安定的な収益確保に結び付くでしょう。
犬の訓練所・しつけ教室・幼稚園
犬の出張(訪問)訓練士・ドッグトレーナー
ペットシッター・お散歩代行サービス開業
核家族化や夫婦共働き家庭の増加傾向により、留守中のペットのお世話をするペットシッターの需要が拡大傾向です。
留守中の給餌やトイレの処理のみならず、溺愛による分離不安で、単独での留守番やペットホテルの利用が出来ないペットが増えていることも一因かと思われます。
犬のお散歩代行についても、飼い主の高齢化にともない、今後益々需要が高まる可能性の高いビジネスです。
これらの市場についても、大手の参入が少なく、小規模事業者の参入の余地が多く残されていると言えるでしょう。
成功の鍵は、ホームページやSNSを利用して如何に集客できるか?
送迎の効率を考えると、地域密着型のビジネスに徹することが重要であり、地域名を織り込んだSEO対策やMEO対策、そしてSNSとの連携が重要となります。
ペットシッター業やお散歩代行業単体での収益性には疑問が残りますが、ペットに対する総合訪問サービスと言う位置づけのビジネスモデルを構築すれば、幅広いお客様からの依頼が見込め、客単価と収益性の向上が可能です。
- シッターやお散歩代行+訪問美容
- シッターやお散歩代行+訪問美容+訪問介護
また、最近ではコンビニエンスストアやファーストフード店でも宅配を兼業するように、有店舗でのペットビジネス(ペットショップ・ペット美容室・ペットホテル等)における訪問サービス兼業は、スタッフの有効活用や収益拡大に大きな効果をもたらす事でしょう。
いずれのビジネスも、第一種動物取扱業の「保管」での登録で起業・開業が可能です。
行政への手続きは一度で済みますので、複合的なビジネス展開も容易に行うことができます。
ペットシッター・犬のお散歩代行サービス
訪問(出張)美容サービス
ペットショップ開業
ペットショップの市場は大手がひしめき合い、決して容易い市場とは言えません。
特に生体販売については、仕入れ価格の高騰などが影響し、小規模ショップの経営を圧迫しています。
ペット用品販売についても、大手ペットショップのみならず、ホームセンター、ネット通販会社等が競合となり、レッドオーシャンと言えるでしょう。
しかしながら、生体販売に頼らず、販売した生体への細やかなアフターサポートにより、その後の消費、併設する美容やペットホテル他のサービスで成果を上げる小規模店は数多く存在します。
小規模事業者の新規参入のハードルは高いですが、生体や用品の販売に頼らない、地域密着型の個性的な店舗運営を目指せば成功の可能性が見出せるでしょう。
また、ブリーダーが自家繁殖の生体販売をメインとするブリーダーズショップについては、利益率が高いうえにインターネット仲介サイトの併用することで広域からの集客できることから、成功の可能性を見出せるビジネススタイルです。
販売した生体へのアフタービジネス(美容・ホテル・訓練・デイサービス等)を取り入れることで、安定的な収益確保につながるでしょう。
哺乳類、鳥類、爬虫類を販売するペットショップ
哺乳類、鳥類、爬虫類を販売しないペットショップ
訪問ペット介護・老犬、老猫ホーム開業
ペットの訪問介護については、ペットブームによる飼養頭数の増加と長寿化により、人間の介護と同様、今後益々需要が高まると共に、競合が少ないブルーオーシャン市場であり、小規模事業者の参入も容易と言えます。
飼い主の老齢化により、ペットを飼養中の飼い主の死亡や介護施設への入所で飼養困難となる事例は増加の一途を辿っており、今後も市場の拡大が予想されます。
成功の鍵は、ホームページやSNSを利用して如何に集客できるか?と言うこと。
送迎の効率を考えると、地域密着型のビジネスに徹することが重要であり、地域名を織り込んだSEO対策やMEO対策、そしてSNSとの連携が重要となります。
そして更には、「ペット介護」と言うサービスが存在すること自体の認知を広める情報発信が非常に重要です。
老犬・老猫ホームについては賛否両論があろうかと思いますが、今後、人間とペットの両者にとって必要不可欠なサービスになることは間違いありません。
人間の介護施設や高齢者向けマンション等と老犬・老猫ホームの併設も、非常に興味深いビジネスと言えるでしょう。
ペットの訪問介護サービス
老犬ホーム・老猫ホーム
その他ペットビジネス開業
ドッグラン・ドッグカフェ・ペット写真館・ペットの温泉、プール・ペットのフィットネスクラブ・ペットの民泊サービス・里親マッチング・ペットの葬儀、埋葬、霊園etc…
ペットのコンパニオンアニマル化と長寿化により、人間並みのサービスへの需要が高まっており、ペットに対する各種サービス分野のビジネス市場は拡大の一途を辿っています。
比較的大手の進出が少なく、アイデア次第で小希望事業者の参入の余地は充分にあると言えるでしょう。